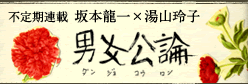「Ryuichi Sakamoto Playing The Piano 2009」をどこで体験すべきか?イビサからシンガポール、北京、モスクワまで「世界のダンスフロア滞留時間が一番多い40代(たぶん)」という熟年クラバーの私は、人間が演奏する音楽は、その"場"というものに大きく作用される、という考え方に大きく寄っている。ホールの音響や歴史、その地の温度や湿度や空気、そして、コンサートはクラブではないので、オーディエンスは、演奏者に関与できないが、確実に存在するはずの"気"のようなものは、表現に影響すると思うからだ。
というわけで、今回、私が選んだのは最北端の札幌公演。その理由のひとつは、教授の新アルバムのサウンドが、どうしようもなく、"北"の音だったからである。北極圏のグリーンランドの海中音が取り入れられていることも関係しているのかもしれないが、全体的にチルであり、空気が薄くて、高度と緯度、光度が高い、という印象。そんな音を、まんま、最北の空気の中で聴いてみたかったのですね。まあ、あとひとつは、客席がステージを取り囲むサラウンド型の音響の名所、札幌コンサートホール Kitaraの響きを体験してみたかったということもあった。
前日の夕方に札幌に到着して、その夜は日本酒と海鮮三昧。翌日は小樽に行ったり、札幌の街を散策したり、藻岩山に登ったりして目一杯、観光する。昼の札幌の街はとにかく、スペースが雄大でヌケがいい。ひしめき合う雑居ビルと街のコマーシャルな騒音になれている身にとっては、この距離感と空間の感覚はかなり非現実的ではある。エヴァンゲリオンの冒頭で、無人の住宅地に使徒がヌーッと立ち現れる場面があるが、あの明るくて空虚な感じが街の至る所に存在するのだ。
陽が落ちるのは早く、オレンジの光の中タクシーを走らせて、ホールに到着した。建物はモダンで新しく、木を多用した暖かみのあるルックス。そういえば、私にとっての坂本ワールド耽溺のきっかけとなった、バルセロナでの地元交響楽団とのドボルザーク「新世界」共演の舞台、オーディトリというホールも、ウッディなサラウンド型だったということを思い出す。
客席の照明は消され、暗がりの中のスクリーンにはアブストラクトなイメージが映し出される。真っ暗闇の中に音が鳴り始めた。かすかな弱音が時間をかけて、その音量を上げていく。曲目は「glacier」。最初のリーン、という鈴の音が垂直に立ち上がって、空間に消えていった。観客はこの冒頭の演出で、一気に日常を断ち切り、坂本龍一の音楽を聴くためのモ耳の禊ぎモをさせられるというわけだ。北の氷の海の中を重力とともに静かに落ちていく自分の身体を想像して心をゆだねてみる。そうして、深海を沈みきった後は、「improvisation」「to stanford」と光の中を浮上していき、midiで自動演奏するもう一台のピアノとの掛け合いでの「hibari」へと続く。
コンサート中の恒例となっていた「composition 0919」の観客参加のケータイフラッシュは、まるで、ジェームス・タレルのインスタレーションのようだ。それから、「high heels」。教授の作るマイナーコードの音楽は、ショパン風のよろめきとメランコリックとラテンの濃厚な夜が出会ったような不思議な魅力があるのだが、スペインの天才監督ペドロ・アルモドバルの『ハイヒール』の主題歌(これ、坂本龍一作品だったのだ!)は、まさにそんなエロティックな魅力に満ちた美曲だった。まるで北海道の澄んだ空気のような「ambiguous lucidity」やラヴェルのマ・メール・ロア風味がたまらない「fountain」を経て、この夜の信じられない成果のひとつである「tango」が登場する。
先ほどの「high heels」でほどかれた情感が、いったん地下に潜った後、ほとばしり出たというような、という感じだろうか。しかし、そのパワーはそれと同等の制御がなされ、情に耽溺することなく、ある意味クールに、刻々と色彩を変える旋律が最も的確な抑揚とピアノ運びで語られていく。
サラウンド型ホールのいいところは、プレイヤーを横、後ろとイレギュラーな位置から見ることができるという点である。私の席からは教授の手元、そして、何と言っても、グランドピアノの弦とハンマーの部分が丸見えだった。それゆえ、今回は教授のペダリングの様子がバッチリ見えてしまったのだが、この「tango」はその呼吸のようなペダルワークがつくり出す細かい表情、そして音響に完全に引き込まれてしまった。
ピアノの弦を豊かに共振させておいて、引き際見事に、さっと次の短音一音に移っていく。特にラストの部分、教授はペダルを踏みっぱなしで、その和音の共振をノイジーなまでに許していたが、その音が消えていく何秒間かの見事な陶酔を私は今でも忘れることができない。そこから、「asience」「energy flow」の三曲の流れは、たぶん、音楽の神が降りてきたかのような異様な時間が存在したと思う。
その緊張をMCが解きほぐした以降は、まさにこの夜の第二楽章とも言える、カラフルな坂本ワールドが展開。ある意味ウェットでもある旋律にmidiピアノがフラクタルで硬質なリフを加えていて、いうならば、北海道の暖房が効いた部屋から眺める吹雪感といった趣の「bibo no aozora」、midiピアノがもはや、双子の人格のようにトリッキーに立った「behind the mask」や「happyend」そして、もうもう、思いっきり感情をほとばしらせたような「merry christmas mr. lawrence」に続く。
ラストへの収束は、エンリオ・モリコーネの「1900」にはじまり、そのアンサーソングのようにも聞こえた筑紫哲也のニュース23のテーマ曲「put your hands up」と続き、ラストの「aqua」という流れでなされた。ドボルザークやアイリッシュ民謡のような、骨太い、民族的かつ素朴で大らかなうねりもまた、教授の音楽の魅力のひとつなんですね。
教授自身が、一番の出来! と発言している札幌でのコンサート。
全国ツアーのあまたの都市の中で、「今回のサウンドならば北だ!」と狙いを定めた私も凄いが、サウンド的には「high heels」や「tango」のラテン系のほの暗い情熱の方に大いに感応してしまったわけで、そのセンス・ギャップもまた趣がある。まあ、アイスクリームの天ぷらやカフェ・アフォガートのような美味しさ、っていうことです。
さて、このコンサートを経て分かったことだが、「hibari」という曲は凄い!(もしかしたら、今回のコンサートはこの曲を聴かせ、分からせるためのパフォーマンスだったのではないかとすら思う)アルバムでは一曲目という確信的な位置に置かれたこの曲は、正直、終盤起こってくる曲のズレとメロディー性といったコンセプチュアルな捕らえ以上のものではなかったのだが、この時、この場のライブの暗がりの中での響き方の強度が異様に強いのである。強いどころか、途中ですでにメロディーの輪郭が溶解してしまって、“何か貴重なものの塊”の印象だけが次々に心に送り込まれていくような感覚を覚えた。
光、の印象もありますね。その日の日中、私の視覚を決定していた、高緯度故に独特の明るさを示す札幌の4月の光はこの時、見事に頭の中のBGVとなっていた。観客にとっての"場"の力は、こういうことだったりするのだ。
text/湯山玲子

- 1. glacier
- 2. Improvisation0429
- 3. to stanford
- 4. hibari
- 5. composition 0919
- 6. koko
- 7. fountain
- 8. high heels
- 9. tango
- 10. a flower is not a flower
- 11. amore
- 12. mizu no naka no bagatelle
- 13. aubade
- 14. put your hands up
- 15. merry christmas mr. lawrence
- 16. the last emperor
- 17. bibo no aozora
- 18. SELF PORTRAIT
- 19. Behind the Mask
- 20. tibetan dance
- 21. thousand knives
- 22. parolibre
- 23. aqua
湯山玲子
1960(昭和35)年・東京生まれ。
出版・広告ディレクター。(有)ホウ71代表取締役、日本大学藝術学部文藝学科非常勤講師。
編集を軸としたクリエイティブ・ディレクション、プロデュースを行うほか、自らが寿司を握るユニット「美人寿司」を主宰し、ベルリンはコムデギャルソンのゲリラショップのオープニングで寿司を握るなど日本全国と世界で活動中。著作に『女ひとり寿司』(洋泉社)、『クラブカルチャー!』(毎日新聞出版局)、『女装する女』(新潮社)。プロデュースワークに『星空の庭園 プラネタリウムアフリカーナ』(2006夏六本木ヒルズ展望台)、野宮真貴リサイタル『JOY』(2007春スパイラル)など。