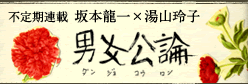ツアーの最終公演は、昭和人見記念講堂である。ここもクラシック分野では、音響に定評がある場所であるが、ある意味、歴史が古くクラシックの古色ふんぷんの会場(なんと、ロビーにどでかい、創立者のブロンズ像が置いてあるのだ!)に、今どきのロン毛やタトゥー有り、が入り混ざった若い人間が集まってくるのを見るのは悪くない。
今回のコンサートの構成の特徴は、導入部に暗がりの中で新アルバムからの打ち込み、音響系を置いて、観客それぞれが持ち込んでいる日常の塵芥をイレースし(そういえば、この感じは、ヨガで心に在る雑念を追い払うメソッドにとってもよく似ている)、その後にスムーズにデリケートなピアニズムの世界に誘い込むというものだ。
グリーンランドの氷の水中のサウンドスケープ「glacier」がまず最初に空気を作っていく。しかし、その次に続くインプロビゼーションの曲調は札幌での大らかさとは全く違う、一気に不安定さに人を誘う現代音楽仕様。「glacier」からさらに深く潜っていく感じで、瞑想度はこちらの方がより高い。どうなるのかな、と思っていたところに、コトリンゴ作の「to stanford」で見事に地上に生還。そして、そのあとに待望の「hibari」がやってきた。
この時の「hibari」は、札幌から時を経て、もうひとつ先の聞こえ方がした。それは、もしかしたら、自分の産まれたときから、常にそばに在って、鳴っていたのではないか?」というような不思議な固着感。何度も繰り返されるフレーズの背骨である「ミ・ラ・ソ・ミ」の4音は、アイルランド民謡の「ダニーボーイ」にもあり、なぜだか、人を郷愁の気持ちにさせてしまう。それは、人それぞれにある個別の故郷の思い出ではなく、いわば人間の共有感覚に訴えかけてくる根源的なものへの郷愁だ。
この曲は、だから、メロディーの天才作家である坂本龍一が、21世紀以降の音響と音圧、そして環境的な音楽の在り方の中で出した、ひとつの回答なのだろう。アルバム「out of noise」では、「まるで美しいメロディーを聴いたような」音響がたくさん詰まっている。私は鈴と笙の「tama」を聴きながら、その魅力に感応できる、過去の素晴らしいメロディーを思い浮かべることができた。とすれば、「hibari」はメロディーと音響のちょうど中間にあるような曲でもある。本当に世界に必要なメロディーはこの10個の音で事足りてしまうのかもしれない。
「fountain」「high heels」「tango」という、札幌公演で最も興奮した「tango」を頂点とした黄金の「ショパンメランコリックとラテンの濃厚な夜」群は、今回はなぜだか、非常に淡々とクールなタッチで展開。これに、セクシーで狂おしい名曲「a flower is not a flower」、「amore」と続くが温度は上がることがない。となると、これらの曲群は、洗練とデカダンの境地という別な表情を見せる。京都は祇園の老妓に凄まじくカッコいいタイプがいるが、そういう風情。
その"抑制の情熱"は、「mizu no naka no bagatelle」の静謐で深まり、「aubade」で明るさを取り戻し、「put your hands up」で大団円を迎え、「merry christmas mr. Lawrence」へと続く。さて、この時のこの演奏の素晴らしさを、どう表現したらいいものか・・・・。「fountain」から地下深く煮えたぎっていた情熱が、一気に吹き出し、ピアノが鳴り響いて大カタルシスを迎えた。「どうしようかなあ~。どっちの方向に行くか。しょうがないかなぁ」という教授の MCの後には、「ラスト・エンペラー」。しょうがないかなぁ、とおっしゃるわりには、豊かでエモーショナルなプレイ。
「bibo no aozora」「self portrait」と続き、「behind the mask」へ。この覚醒的な曲でふと我に返り、すでにコンサートは終盤に向かっていることに気がついた。「tibetan dance」はさらっとしたタッチながら、アフタービートの応酬をじっくりと味わう。ヨナ抜きペンタトニックのリズミカルな「thousandknives」、を経て「parorible」で本格的に黄昏れ感とともにエンディングに入っていく。
これで終演かと思ったら、会場に終演放送が流れる中、教授は再びステージに登場した。「お帰りになって下さらないので~(笑)」というMCのあとに何と、手すさび風のジャズ・インプロを数小節披露した。ラストはやはり「aqua」。イントロでフフッと笑ったのは、これ、もう、ラストの定番だったからでしょうね。そう、いわば坂本学校の下校の音楽。坂本版「夕焼け小焼け」を後にして、観客はそれぞれの家路に帰ったのだった。
私の行きつけのひとつである三軒茶屋の某バーに立ち寄って、そこの抜群に良いステレオでi podDJにて、一晩中教授曲をハードプレイ。コンサートに行った何人かは、その夜、東京で同じことをやったのでしょうね!
text/湯山玲子

- 1. glacier
- 2. Improvisation0429
- 3. to stanford
- 4. hibari
- 5. composition 0919
- 6. koko
- 7. fountain
- 8. high heels
- 9. tango
- 10. a flower is not a flower
- 11. amore
- 12. mizu no naka no bagatelle
- 13. aubade
- 14. put your hands up
- 15. merry christmas mr. lawrence
- 16. the last emperor
- 17. bibo no aozora
- 18. SELF PORTRAIT
- 19. Behind the Mask
- 20. tibetan dance
- 21. thousand knives
- 22. parolibre
- 23. aqua
湯山玲子
1960(昭和35)年・東京生まれ。
出版・広告ディレクター。(有)ホウ71代表取締役、日本大学藝術学部文藝学科非常勤講師。
編集を軸としたクリエイティブ・ディレクション、プロデュースを行うほか、自らが寿司を握るユニット「美人寿司」を主宰し、ベルリンはコムデギャルソンのゲリラショップのオープニングで寿司を握るなど日本全国と世界で活動中。著作に『女ひとり寿司』(洋泉社)、『クラブカルチャー!』(毎日新聞出版局)、『女装する女』(新潮社)。プロデュースワークに『星空の庭園 プラネタリウムアフリカーナ』(2006夏六本木ヒルズ展望台)、野宮真貴リサイタル『JOY』(2007春スパイラル)など。